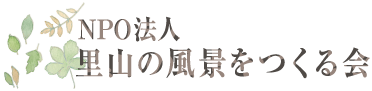つげ義春さんのマンガで忘れられないシーンがある。
その最後のシーンだけが記憶に残っているのだ。
途中は忘れてしまっている。どんなストーリーだったっけ。
少年が一人で仕事をしている。
町工場の片すみで。
子供のころ、普通に目にしたバラックのような板張りの工場の中で・・・。
書庫の一番奥の棚にあったつげ義春全集を引っぱり出した。
その第7巻に出ている「大場電気鍍金工業所」がそれであった。
メッキ工場の社長が肺炎で死んでしまい、
残された奥さんとメッキ工の少年が工場で研磨の賃仕事をしている。
「メッキの職人は必ず肺をやられる」と、出だしから暗い話ではある。
このマンガは、つげ義春さんの自伝的作品で、メッキ工の少年は作者の分身である。
元工場長の金子さんとその家族の描写は、これ以上ないのではという程悲惨であるが、
読んでいるとなぜか懐かしい気分になってくる。
確かにこんな風だったよな、あのころは、と思えてくるのである。
つげ義春さんは1937年生まれだから、私より14歳上だ。
小学校を卒業してメッキ工になった。
メッキ工場に行きながらマンガを書き始めた。
しかしなかなか芽が出ず、東京錦糸町の下宿の支払いを2年分も留めたため、
便所を改造した一畳の部屋に幽閉されている。
そこで8年間過ごすことになる。そのころのことを描いたのが「義男の青春」である。
やがて白土三平さんに認められ、『ガロ』で作品が掲載されるようになる。
「紅い花」や「李さん一家」「ねじ式」など、
つげさんの代表作が生み出されていくのである。
私はつげさんのほとんどの作品を読んでいて、どれも大好きなのだが、
自伝的作品には特に心引かれる。
そこにはあの時代の貧乏で孤独な青年と、
無名の職人たちや生活者の姿が描き込まれているのである。
みんな同じように貧乏だったけど、心は貧しくなかったあのころ。
「大場電気鍍金工業所」の中で、奥さんが男とともに夜逃げしてしまい、
人手に渡ってしまった工場で、ひとり研磨機に向かう少年。
その印象的な最後のシーンが心から離れないのである。
建築家 野口政司 2010年 3月 12日(金) 徳島新聞夕刊 「ぞめき」より